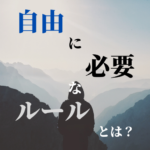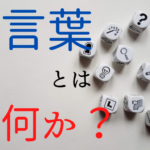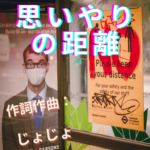なぜクイズは生まれたか?

茂木健一郎氏が東大生の参加するクイズ番組を批判したことをヤフーが報じた。
これについて、ネタ切れの私も記事にしてみたいと思う。私が思うに、クイズなんて、何の価値も生み出さない競技で、たぶんグーグルが参戦すれば絶対優勝が目に見えている「遊び」であろう。なぜなら、クイズとは「検証」性と「納得」性が重要で、「エビデンス」と「再現性」がなければ意味がない。例えば、コインを投げて「裏」か「表」かを当てる確率を競うゲームはクイズとは言わないだろう。
つまりクイズとは過去の経験や事実に基づいて、それが正しい唯一の答えであることが、多数の人に理解できるレベルで保障される「正解」を提示できる問題集であると言える。要するに過去にすでに証明されている、あるいは確認されている事象しか問題にならないという意味でクイズをすることによって何も新しい価値は生み出さないのである。
にもかかわらず、クイズがテレビ番組として「成立」する理由は何か?
おそらくテレビが発達する前、日本人の知識レベルは地方によって格差があったに違いない。また、それくらい昔であれば、人々の「知識」に対する欲求は相当高かったと思われる。
たとえば農耕社会において、天気は重要な関心事であった。したがって、明日雨が降るか、陽が射すかは重要な関心事であった。つまり、天気に関する知識を持つものは重宝がられたと思う。また、村はずれの道の先がどこに通じているかというような、地理に関する知識を持っているものもまた重宝がられたであろう。つまり、「知識」を持っていることは生きていくうえで、重要なメリットになったわけである。
そんな社会に「テレビ」が登場し、その番組の中で、面白おかしく「知識」を伝えてくれれば、日本人の手っ取り早い知識レベルアップにつながり、日本全体の状況の理解もしやすくなるので、皆テレビにくぎ付けになるだろう。そんな経験を子供のころにすれば、その刷り込みが続く限り、永遠にクイズ番組はなくならないし、知識はめったに陳腐化しないので、はやりすたりのある「ドラマ」や「歌番組」より息の長いメニューになるのは当然である。
このように、クイズ番組は「知識」に対する人間(日本人?)の憧れの表れであると言える。
東大生がクイズに参加することの意味するものとは?
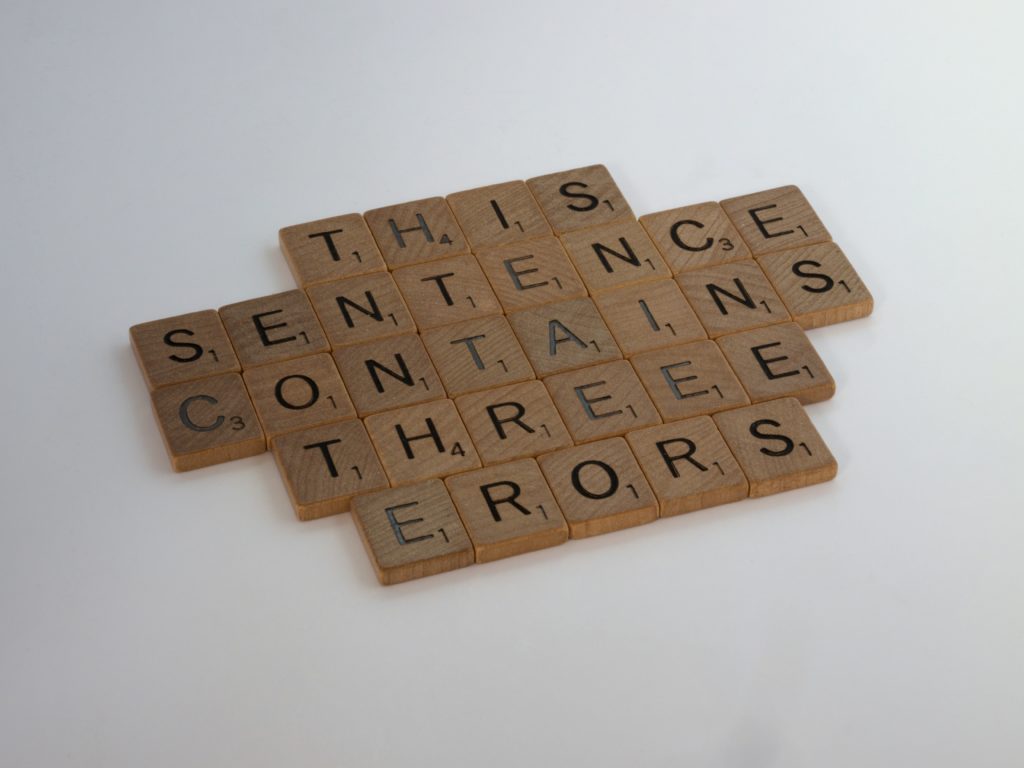
しかし、上記の茂木氏の批判は、クイズ番組自体に向けられているものではない。「東大生」の参加ということがポイントなのである。
昔から、東大生=クイズ王という番組は、長いテレビの歴史の中でも作られたことはなかった。これはなぜかというと、明確な答えはないのだが、私の仮説はこうである。
そもそも昔は大学進学率は低かった。だからこそ、高度経済成長の中で、社畜として煮え湯を飲まされてきた底辺サラリーマンたちは、一生懸命自分の子供を「大学」へ進学させようとした。「学歴」というレッテルで人間の能力を判断した方が、誰がやっても同じ結果が出る「大量生産」時代の人間評価としては全員の納得が得られやすかったからである。
このことは逆に言うと日本人の大半が「学歴コンプレックス」を持っていたことになる。つまり、テレビ番組で、クイズで活躍する大学生、ましてや東大生などを映しても、茶の間はしらけ切って視聴率が取れるわけはなかったのである。普通の会社員や主婦、無名の高校生当たりの活躍が、茶の間のジャパニーズサラリーマンの琴線に触れたのである。
しかし、高度成長を終え、安定成長、あるいはゼロ成長時代を迎え、一億総中流社会意識の中で、大学進学率も過半数になりおおむね病的な学歴コンプレックスが国民から消えつつある段階において、「大学生」がクイズで活躍しても不快に思われなくなり、とうとう、今まで「控えていた」東大生の活躍するクイズ番組が作られるようになったのだと思う。
まあこれもある種の「学歴コンプレックス」の裏返しなのだろうと思う。「病的か」「正常の範囲か」の違いはあっても、東大生=「頭いい」=「クイズが得意」という単純な方程式を思い浮かべてしまうことは、「普通」なのかもしれないが、ある意味において、私は異常だと思う。
過去の経験や知識が役に立つのは、あくまで「変化のない世界」でだけのことであって、かつて村社会で重宝された長老の経験も、今や「老害」とされて忌み嫌われる時代である。このような激動の時代にあって、日本を代表するはずの知識集団である「東大生」が単なる「字引」で満足しているようではなさけない。
やはり、集団化した人間社会は、本質が「平均値」に近づくだけなので、社会をリードするようなカリスマ的リーダーは、「平均値」の社会が生み出した「東大生」という平均的天才集団からは生まれないのかもしれない。
誰の助けも受けず、社会から無視されていたアウトローがある日突然ウルトラヒーローに「変身」してくれる日を、我々庶民はひたすら待ち続けなければいけないのかもしれない。